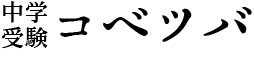この記事では四谷大塚生、早稲田アカデミー生、英進館生など、全国の予習シリーズ生が利用する「週テスト」「カリキュラムテスト」(算数)について、目的・特徴や出典・難易度、対策方法をお話します。記事の内容は以下のラジオでもご紹介しておりますので、よろしければご視聴ください。
はじめに ~週単位の学習の重要性と”桶狭間の戦い”~
1:59から再生
家庭教師として長年指導してきた経験から、志望校対策の本格的な学習以前の段階で最も重要なのは「週単位の学習」の強化です。多くの集団塾は週単位でカリキュラムを組んでおり、子どもたちはこの期間で新しい技術や論点を習得することが求められます。2020年代の塾では「余分なこと」はほとんど教えないため、週単位で習得できなかった技術は「穴」として残ってしまいます。したがって、週単位での学習の網羅性と定着性が鍵を握ります。
もちろん以前からの穴を埋めることも必要ですが、何より新たな穴を作らないことが重要です。子どもたちが本気で学習する期間を約1-3年間と考えると、「週単位の学習でアクセルを踏んでもらえるか、伴走者としては踏ませられるか」が最も大切なのです。受験はマラソンのようなもので、中盤や終盤の調整も大事ですが、序盤の走り方を調整するだけで志望校に合格できることも多いのです。
四谷大塚の週テストや早稲田アカデミーのカリキュラムテストで点数が上がれば、つまり週単位の学習の成果が目に見えれば、子どもは成功体験として新しい学習法を自分のものにし、嬉しそうに努力するようになります。自分の成長に希望を持ちながら学習を進める状況を作ることが、伴走者として最初に取り組むべき重要な戦いです。
学習方法を変えることには誰でも抵抗を感じますが、それを乗り越えるのは「期待」や「希望」です。そして継続の原動力となるのは「実感としての成果」、つまり週テストの結果ということです。
こうした「努力の甲斐があった!」という最初の一歩を創り出し、それを毎週続けて行ける状態を作るまでを、”桶狭間の戦い”と呼んでいます。入試までの全体プロセスを俯瞰して見ても、受験学年よりも前段階でいきなり訪れるものの、相当に重要度が高いものだと考えております。
以下では、週単位の学習方法についてご説明していきます。参考にしていただくことで、それぞれの「学びの桶狭間」を無事に切り抜けていただければ幸いです。
週テスト・カリキュラムテストの目的
10:37から再生
「週テスト」「カリキュラムテスト」は、四谷大塚が開催する2種類の確認テストです。算数はコース別(S・C・B・A)のテストとなっており、平均点や偏差値・全国の順位が発表されます。
週テスト:1週間に1回、直営校や一部の準拠塾で実施されるもの
カリキュラムテスト:2週間に1回、早稲田アカデミーを筆頭とする提携塾で実施されるもの
これらのテストの内容は、簡潔に言うと「先週と今週で学習した技術・論点」を自由に使いこなすことができているかを問うものになっています。つまり、1-2週間の学習で身につけるべきものの「穴」がないかどうかを測る目的で設計されています。また、週報などで偏差値や順位が出るため、子どもたちも頑張る動機に繋がりやすいことが特徴です。
逆に、ご家庭チームとしては、週単位の学習における「努力の量や質」が適切かどうかを測るための指標として活用することができます。効率的な学習のために週テスト・カリキュラムテストという機会を活かす、という認識で進めていくのがよいでしょう。
穴を発見して、後々埋めなければいけないことを把握するためのセンサー
やり方を変えた時に結果としてすぐに反映されるため、変更後の学習効果を判断する指標
週テスト・カリキュラムテストの分析
14:41から再生
テストの構成や平均点
週テストの構成

構成はほぼ完全に固定されているため、「できなかった論点が、今週の内容なのか?先週の内容なのか?」を明らかにして、次に活かしてほしいと思います。特徴的な点は、今週の論点や技術を完全に理解していても60%までしか得点できないことです。例えば、子どもたちが「生まれ変わるように決意して一週間頑張った」としても、前週の内容に穴がある場合、極端に言うと75点しか取ることはできません。しかしその場合も「今週の内容はできていたこと」を賞賛すべきということになります。
週テストのおおよその平均点
学年・コースによらず、おおよそ55-70点が平均になっております。No.によってのブレはおおよそ上のレンジに収まる範囲が多いですが、難易度の高いNo.であれば50-55点、簡単もしくは仕上がったお子様が多く受験する6年生中盤であれば70点以上という場合もあります。
カリキュラムテストの構成

四則演算を除いた2週間分の小問集合と大問がほぼ均等に出題される構成で、週テスト2週間分を凝縮した形になっています。
出題範囲とクラス帯による違い
テストの問題が【どのテキストの、どのレベルの問題】をベースに作られているかを推論したものを記載します。

4-5年生
ABクラス:予習シリーズと演習問題集のトレーニングまでを中心に出題される
CSクラス:予習シリーズ・演習問題集・最難関問題集を中心に出題される
※Sクラスの方が応用・発展問題が1問多い
6年生
ABクラス:予習シリーズと演習問題集のステップ①までを中心に出題される
CSクラス:予習シリーズ・演習問題集・最難関問題集を中心に出題される
※Sクラスの方が応用・発展問題が1問多い
出題されている論点の傾向は、週テストもカリキュラムテストも同じです。クラス帯によって出題されるテキストの範囲が大きく異なるという点が大きな特徴です。結果として、学力上位帯でもそれに比例してテストの難易度が上がることから、平均点がほぼ一定になっています。
ABクラスは「予習シリーズ」が中心、「演習問題集」のトレーニングまでで構成される
CSクラスは「最難関問題集」まで含むすべての問題集で扱った論点が範囲に入っている
Cでは最後の1問、Sでは最後の2問で「応用・発展問題」が出題され難易度が高くなっている
テストの特徴
他の有名塾との明確な違いは、学年・クラス帯によらずテキスト問題と数値を変えただけの全く同じ問題は出題されないことです。ただし、「テキストに掲載されている技術を使う」という制約条件の中で問題が設計されています。その上で最低でも、数値だけではなく、文章を変えるところまでを意図して出題されていることが伺えます。
下位クラスであっても数値替え問題を出題しないことから、算数の初学者や算数が苦手な人には比較的厳しい構成になっています。あまりの得点の取れなさに、テスト自体に消極的になってしまう可能性もあるでしょう(もちろん、本来はそれでも得点できるよう訓練するプロセス自体が、学力の伸びと正しい学習スタイルの形成につながり、とても大事ではあります)。
反面で、数値替え問題に慣れ、解法を理解せずただ暗記しているだけで乗り切ろうとする人をあぶり出すことができる構成になっているとも言えます。4〜5年生の算数を暗記だけで乗り切ってしまった場合、滑り出しは高得点でも徐々に成績が低下し、6年生では通用しなくなってしまいますが、こうしたケースが四谷大塚のテストで訓練されてきた子供たちには少ないと言えるでしょう。
また、クラス帯ごとにテスト内容を細かく替えており、上位帯の中でもテストで差がつく構成になっていることから、週テストの成績が組分けの成績と相関しやすいと推測されます。
週テスト・カリキュラムテストに向けた対策と学習方法
25:28から再生
学習法の大まかな流れは、週テストもカリキュラムテストも難易度レベルは同様となり、大差はありません。毎週(今週1週間)の学習について説明したのち、「先週のNo.の復習」について説明いたします。
毎週の学習(コベツバを利用する場合)
以下の流れで、新しく習うNo.の学習を一週間でおこないます。
1:授業前にポイント動画を見る(例題と類題があれば、解いておく)
2:授業を受ける
3:授業後目安48時間以内に、同じポイントを使う問題ごとに、教材を横断して連続で解く
4:同時に、1問ごとに問題に記号を打つ+やり直しをすぐにおこなう
5:次回の週テストまでに、◎以外の問題を再度やり直す
1:授業前にポイント動画を見る(例題と類題があれば、解いておく)
学習する論点を端的にまとめた「ポイント動画」を見て授業に臨むことを推奨します。多くのコベツバユーザー様から、「先にポイント動画を見てから授業を受けると、理解が早く、学習全体の時間短縮に繋がる」というお声をよくいただいています。
なお、実際に例題・類題まで手を動かすほうがより授業の理解は進むでしょうが、授業後にやる場合と比べた時にどちらが効率的かは、お子様・通っている塾の先生のスタイルによります。ご家庭で相談してお決めいただくとよいでしょう。
2:授業を受ける
3:授業後目安48時間以内に、同じポイントを使う問題ごとに、教材を横断して連続で解く
コベツバでは、同じポイントを使う問題をまとめて学習いただけます。同じポイントを使う問題を連続して解いていくことで、より体系的に学習することができます。
四谷大塚の教材は演習に寄った作りになっていますが、新出の技術を身につける段階においては「同じ技術を、異なる問題・異なる角度で何問か経験する」ことでようやく身につけることができるため、コベツバでは「同じポイントを使う問題をまとめて解く」ことをおすすめします。
4:同時に、1問ごとに問題に記号を打つ+やり直しをすぐにおこなう
答え合わせとやり直しは、必ず1問ごとにおこないましょう。1問ごとに答え合わせ・やり直しをしない場合、同じ間違いを何度も繰り返してから一気に直すことになりますし、分からない問題が何問も続くことがあるためです。
そして、動画を見て理解しただけで終わらずに「必ず動画を見ずに自分の手で解いてみる」ことが重要です。大多数のお子様において「動画を見てわかったとしても実際に手を動かすと解けない」と言うことがあり得ます。必ず「自分の手で解けるか」までを確かめておきましょう。
最後に、問題と向き合った場合には、以下の記号を打つ習慣をつけましょう。
◎:正解し、次の週テスト時点でも絶対に大丈夫と言い切れる問題
◯:正解し、次の週テストまでに一度見直しておかないと忘れそうな問題
△:正解したものの、解き方に不安が残る or 時間が(解説動画の時間以上)かかった問題
×:不正解 or 途中で諦めた問題
5:次回の週テストまでに、◎以外の問題を再度やり直す
4で打った記号のうち、◎以外の問題をすべてやり直して定着確認をおこないます。もちろん、間違った問題は解説を見て解き直し、ここでも必ず「自分の手で解けるか」の確認までおこないましょう。
毎週の学習(コベツバを利用しない場合)
以下の流れで、新しく習うNo.の学習を一週間でおこないます。
1:授業前は例題と類題に取り組む
2:授業を受ける
3:授業後目安48時間以内に、同じポイントを使う問題ごとに、教材を横断して連続で解く
4:同時に、1問ごとに問題に記号を打つ+やり直しをすぐにおこなう
5:次回の週テストまでに、◎以外の問題を再度やり直す
それぞれの項目の注意点は「コベツバを利用する場合」と大きく変わりませんので、ご参照ください。
ただし、「3:同じポイントを使う問題ごとに、教材を横断して連続で解く」については、以下のページでご確認いただくことがおすすめです。今週登場する重要なポイントに対して、そのポイントを利用する問題を列挙しておりますので、そちらの問題群をセットで学習することが重要です。
<各No.の話をしよう>
先週のNo.の復習
週テスト・カリキュラムテストはもちろんのこと、組分けテストにも活きてくるため「今週の学習と共に前週の見直しまでを習慣化すること」をおすすめします。
もちろん、カリキュラムテストは週テストと違って、2週分のNo.をまとめたテストになっています。例えばNo.1-2が範囲の場合に翌週にNo.2を復習しても、次回のテスト(No.3-4)には出題されることはありませんので、復習の意義は感じがたいかもしれません。それでも、記憶の長期定着、そして組分けテストへの布石になるため、「今週の学習は翌週もう一度復習しておく」習慣をつけておきましょう。
具体的には、1周目の段階でつけられた記号(理解度)を元にやり直しをおこないます。一見すると非常に時間がかかるように思えますが、1周目の時点で丁寧に身につけられていれば短時間で終わるようになるはずです。そこまで到達できれば、週テストやカリキュラムテストでは高得点が期待できる状態になっていることが多いでしょう。
時間がなければ「△と×の問題」をやり直す
時間があれば「○の問題まで、つまり◎の問題以外」をやり直す